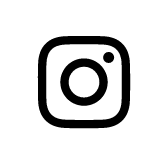- 2025.04.12
-
【2025年6月最新版】解体事業を行う際に必要な許可まとめ
解体工事を行う上で、適切な許可の取得は法令遵守の観点から非常に重要です。本稿では、解体工事業を営む上で必要となる様々な許可について詳しく解説します。建設業においては、その事業活動の特性上、多岐にわたる法規制が存在し、解体工事も例外ではありません。適切な許可を得ずに工事を行うことは、法的な罰則を受けるだけでなく、社会的な信用を失墜させる可能性もあります。
本稿を通じて、解体工事業者が事業を適法かつ円滑に進めるために必要な許可の種類、取得要件、注意点などを網羅的に理解いただくことを目指します。
解体工事の種類と必要な許可
解体工事と一言で言っても、その規模や内容によって必要となる許可は異なります。ここでは、解体工事を行う上で特に重要な許可について、その種類と概要を解説します。
建設業許可
建設業許可は、建設工事の完成を請け負う営業を行うために必要な許可であり、解体工事もその対象となります
- 許可の正式名称: 建設業許可(けんせつぎょうきょか)
- 許可の管轄省庁・機関: 営業所の所在地が二つ以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣、一つの都道府県内のみの場合は当該都道府県知事
- 許可が必要となる工事の範囲・条件: 請負金額が500万円(税込)以上の解体工事を行う場合に必要となります
- 許可取得の要件・手続き: 建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たす必要があります
- 許可の有効期限: 建設業許可の有効期間は5年間であり、期間満了後も引き続き事業を行う場合は更新の手続きが必要です
- 無許可で工事を行った場合の罰則: 請負金額が500万円以上の解体工事を建設業許可なしに行った場合、建設業法に違反する行為となり、罰金や懲役などの罰則が科される可能性があります。
500万円という金額は、解体工事の規模を判断する上で重要な基準となります。この基準を超える工事を請け負うには、国または都道府県からの許可が不可欠であり、許可を得るためには相応の準備と要件を満たす必要があります。また、総合的な企画や調整を伴う大規模な解体工事は、たとえ個々の解体作業の請負金額が500万円未満であっても、一式工事の許可が必要となるケースがあるため注意が必要です。建設業許可には5年の有効期限が定められており、継続して事業を行うためには更新手続きを怠らないことが重要です。無許可での営業は、法的責任を問われるだけでなく、企業としての信頼を大きく損なうため、必ず許可を取得するようにしましょう。
解体工事業許可
平成28年6月1日の建設業法改正により、解体工事を行う事業者は、従来の「とび・土工工事業」の許可に加えて、新たに設けられた「解体工事業」の許可を取得することが原則となりました
- 許可の正式名称: 解体工事業許可(かいたいこうじぎょうきょか)
- 許可の管轄省庁・機関: 営業所の所在地が二つ以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣、一つの都道府県内のみの場合は当該都道府県知事
- 許可が必要となる工事の範囲・条件: 工作物の解体を行う工事であり、特に請負金額が500万円以上の解体工事に必要となります
- 許可取得の要件・手続き: 建設業許可と同様に、経営業務の管理責任者と専任技術者の配置が求められます
- 許可の有効期限: 建設業許可と同様に5年間です(明示的な記載はないものの、建設業許可の一種であるため同様の扱いとなります)。
- 無許可で工事を行った場合の罰則: 請負金額が500万円以上の解体工事を解体工事業許可または適切な建設業許可なしに行った場合、建設業法に違反し、罰則の対象となります。
この解体工事業許可の新設は、解体工事の専門性がより重視されるようになったことを示しています。以前は「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負うことができましたが、法改正により、一定規模以上の解体工事には原則として解体工事業の許可が必要となりました。ただし、大規模で複雑な解体工事の場合は、建築一式工事や土木一式工事の許可が該当する場合もあります。この変更は、解体工事における安全管理や環境対策の重要性が高まっていることの表れと言えるでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事に伴って発生するコンクリートくず、木くず、金属くずなどは産業廃棄物に該当します。これらの産業廃棄物を収集し、運搬するためには、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります
- 許可の正式名称: 産業廃棄物収集運搬業許可(さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうきょか)
- 許可の管轄省庁・機関: 産業廃棄物の積込みを行う場所と荷卸しを行う場所の都道府県知事
- 許可が必要となる工事の範囲・条件: 他の事業者から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合に必要となります
- 許可取得の要件・手続き: 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、講習会の受講修了、経理的基礎、事業計画、運搬施設の要件などを満たす必要があります
- 許可の有効期限: 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間であり、更新が必要です
- 無許可で工事を行った場合の罰則: 他の事業者から委託された産業廃棄物を無許可で収集・運搬した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、罰則が科されます。
解体工事では必ず産業廃棄物が発生するため、その適切な処理は非常に重要です。元請けとして工事を行う場合は、自社で運搬する際に必ずしも許可は必要ありませんが、許可を取得しておくことで、下請けの仕事も幅広く対応できるようになり、事業の機会が広がります
特定建設作業に関する届け出
解体工事の中には、騒音や振動を著しく発生させる作業が含まれる場合があります。これらの作業は、騒音規制法や振動規制法に基づき「特定建設作業」として定められており、作業を開始する前に自治体への届け出が必要です
- 許可の正式名称: 特定建設作業実施届出(とくていけんせつさぎょうじっしとどけで)
- 許可の管轄省庁・機関: 作業を行う地域の市区町村長
- 許可が必要となる工事の範囲・条件: 解体工事において、くい打機、くい抜機、鋼球を用いた建築物の破壊、舗装版破砕機、ブレーカー(手持ち式を除く)など、特定の機械を使用する作業が該当します
- 許可取得の要件・手続き: 届け出書の提出が必要であり、作業の種類、期間、時間、騒音・振動防止対策などを記載します
- 許可の有効期限: 届け出は特定の作業期間に対して行われるため、明確な有効期限はありませんが、期間が変更になる場合は再度届け出が必要となることがあります
- 無許可で工事を行った場合の罰則: 特定建設作業を届け出なしに行った場合、騒音規制法や振動規制法に基づき罰則が科されることがあります。
解体工事における騒音や振動は、周辺住民の生活環境に大きな影響を与える可能性があります。そのため、法令で定められた特定の作業を行う場合は、事前に自治体に届け出て、適切な騒音・振動対策を講じることが求められます。届け出を怠ると罰則の対象となるだけでなく、地域住民とのトラブルにも繋がりかねません。工事を行う前に、使用する機械や作業内容を確認し、特定建設作業に該当する場合は必ず届け出を行いましょう。また、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するなど、可能な限り騒音・振動の抑制に努めることが重要です
その他関連する可能性のある許可
上記以外にも、解体工事の内容によっては必要となる可能性のある許可や届け出が存在します。
- アスベスト関連の許可・届出: 解体する建物にアスベストが含まれている場合は、大気汚染防止法などに基づき、事前に調査を行い、その結果を所轄の労働基準監督署や自治体に報告する必要があります
- 道路使用許可: 解体工事に伴い、工事車両の通行や資材の搬入などで道路を使用する場合や、足場などを道路にはみ出して設置する場合には、所轄の警察署長の道路使用許可が必要となることがあります(本稿の調査範囲では明示的な言及はありませんでした)。
- 建設リサイクル法に基づく届出: 一定規模以上の建築物等の解体工事(床面積80平方メートル以上など)を行う場合は、建設リサイクル法に基づき、工事着手の7日前までに都道府県知事への届け出が必要です
- 車両系建設機械運転技能講習: 解体工事で使用する一定規模以上の重機(油圧ショベル、ブルドーザーなど)を運転するには、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了が必要です
- 作業主任者: 特定の危険な作業(足場の組立て、解体作業、型枠支保工の組立て等)を行う場合には、労働安全衛生法に基づき、作業主任者を選任し、作業を指揮させる必要があります
解体工事は、その対象となる建物や構造物の種類、規模、周辺環境などによって、必要となる許可や届け出が多岐にわたります。アスベストの有無は、解体工事の計画において非常に重要な要素であり、適切な調査と対応が不可欠です。道路の使用や建設資材のリサイクルに関する法律も遵守する必要があります。また、安全な作業を行うためには、適切な資格を持った作業員の配置も重要となります。
まとめ
解体工事を安全かつ適切に進めるためには、それぞれの工事内容に応じて適切な許可を取得することが不可欠です。ご不明な点があれば、専門家への相談をおすすめします。解体工事業を営む上で必要となる許可は、工事の規模や内容、発生する廃棄物の種類、作業に伴う騒音・振動の有無などによって異なります。建設業許可(解体工事業)、産業廃棄物収集運搬業許可、特定建設作業に関する届け出などが主なものとして挙げられますが、アスベスト関連の対応や道路使用許可、建設リサイクル法に基づく届け出なども考慮する必要があります。これらの許可や届け出は、法令遵守だけでなく、安全な作業環境の確保、周辺環境への配慮、そして事業の信頼性向上にも繋がります。常に最新の法規制を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、適切な許可を取得・維持していくことが、解体工事業を健全に発展させるための重要な要素と言えるでしょう。
補足
本稿で解説した許可・届け出に関連する主な法律は以下の通りです。より詳細な情報については、各法律の条文や関連省庁のウェブサイト等をご確認ください。
- 建設業法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 大気汚染防止法
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 労働安全衛生法
この記事を書いたコンサルタント

無料経営相談をご活用ください!
弊社の専門コンサルタントが貴社にご訪問、もしくはお客様に弊社までお越し頂き、現在の貴社の経営について無料でご相談いただけます。 無料経営相談は専門コンサルタントが担当させていただきますので、どのようなテーマでもご相談いただけます。


 0120-958-270
0120-958-270